
藤壺《ふじつぼ》の宮の自邸である三条の宮へ、
様子を知りたさに源氏が行くと王命婦《おうみょうぶ》、
中納言の君、中務《なかつかさ》などという女房が出て応接した。
源氏はよそよそしい扱いをされることに不平であったが
自分をおさえながらただの話をしている時に
兵部卿《ひょうぶきょう》の宮がおいでになった。
源氏が来ていると聞いてこちらの座敷へおいでになった。
貴人らしい、そして艶《えん》な風流男とお見えになる宮を、
このまま女にした顔を源氏は かりに考えてみても それは美人らしく思えた。
藤壺の宮の兄君で、また可憐な若紫の父君であることに
ことさら親しみを覚えて源氏はいろいろな話をしていた。
兵部卿の宮もこれまでよりも打ち解けて見える美しい源氏を、
婿であるなどとはお知りにならないで、
この人を女にしてみたいなどと若々しく考えておいでになった。
夜になると兵部卿の宮は
女御の宮のお座敷のほうへ はいっておしまいになった。
源氏はうらやましくて、
昔は陛下が愛子として
よく藤壺の御簾《みす》の中へ自分をお入れになり、
今日のように 取り次ぎが中に立つ話ではなしに、
宮口ずからのお話が伺えたものであると思うと、
今の宮が恨めしかった。
「たびたび伺うはずですが、
参っても御用がないと自然 怠けることになります。
命じてくださることがありましたら、
御遠慮なく言っておつかわしくださいましたら満足です」
などと堅い挨拶をして源氏は帰って行った。
王命婦も策動のしようがなかった。
宮のお気持ちをそれとなく観察してみても、
自分の運命の陥擠《かんせい》であるものはこの恋である、
源氏を忘れないことは自分を滅ぼす道であるということを
過去よりもまた強く思っておいでになる御様子であったから
手が出ないのである。
はかない恋であると消極的に悲しむ人は藤壺の宮であって、
積極的に思いつめている人は源氏の君であった。
少納言は思いのほかの幸福が小女王の運命に現われてきたことを、
死んだ尼君が絶え間ない祈願に愛孫のことを言って
仏にすがったその効験《ききめ》であろうと思うのであったが、
権力の強い左大臣家に第一の夫人があることであるし、
そこかしこに愛人を持つ源氏であることを思うと、
真実の結婚を見るころになって面倒が多くなり、
姫君に苦労が始まるのではないかと恐れていた。
しかしこれには特異性がある。
少女の日にすでにこんなに愛している源氏であるから
将来もたのもしいわけであると見えた。
少納言のホームページ 源氏物語&古典 syounagon-web ぜひご覧ください🪷
https://syounagon-web-1.jimdosite.com
💠源氏物語 第七帖 紅葉賀💠(前半)
世間は朱雀院で開かれる紅葉賀に向けての準備でかまびすしい。
桐壺帝は最愛の藤壺が懐妊した喜びに酔いしれ、
一の院の五十歳の誕生日の式典という慶事を
より盛大なものにしようという意向を示しているため、
臣下たちも舞楽の準備で浮き立っている。
ところが、
それほどまでに望まれていた藤壺の子は桐壺帝の御子ではなく、
その最愛の息子光源氏の子であった。
このことが右大臣側の勢力、特に東宮の母で藤壺のライバル、
また源氏の母を迫害した張本人である弘徽殿女御に発覚したら
二人の破滅は確実なのだが、
若い源氏は向こう見ずにも藤壺に手紙を送り、
また親しい女官を通して面会を求め続けていた。
一方で、
藤壺は立后を控え狂喜する帝の姿に罪悪感を覚えながらも、
一人秘密を抱えとおす決意をし、
源氏との一切の交流を持とうとしない。
源氏は
そのため華やかな式典で舞を披露することになっても浮かない顔のままで、
唯一の慰めは
北山から引き取ってきた藤壺の姪に当たる少女若紫(後の紫の上)の
無邪気に人形遊びなどをする姿であった。
帝は式典に参加できない藤壺のために、
特別に手の込んだ試楽(リハーサル)を宮中で催すことに決める。
源氏は青海波の舞を舞いながら御簾の奥の藤壺へ視線を送り、
藤壺も一瞬罪の意識を離れて源氏の美貌を認める。
源氏を憎む弘徽殿女御は、舞を見て
「まことに神が愛でて、さらわれそうな美しさだこと。おお怖い。」
と皮肉り、
同席していたほかの女房などは「なんて意地の悪いことを」と噂する。
紅葉の中見事に舞を終えた翌日、
源氏はそれとは解らぬように藤壺に文を送ったところ、
思いがけず返事が届き胸を躍らせた。
五十の賀の後、源氏は正三位に。
頭中将は正四位下に叙位される。
この褒美に弘徽殿女御は「偏愛がすぎる」と不満を露わにし、
東宮に窘められる。
翌年二月、藤壺は無事男御子(後の冷泉帝)を出産。
桐壺帝は最愛の源氏にそっくりな美しい皇子を再び得て喜んだが、
それを見る源氏と藤壺は内心罪の意識に苛まれるのだった。
💠聴く古典文学📚少納言チャンネルは、聴く古典として動画を作っております。ぜひチャンネル登録お願いします🌷

- 価格: 18000 円
- 楽天で詳細を見る
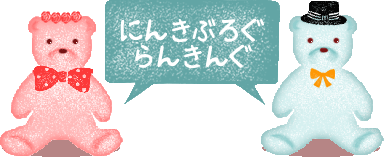
![【ふるさと納税】篠笛楽遂 ドレミ調八笨調子 (C調) 姿仕上げ、笛袋と篠製こはぜ付き|甘楽町 篠笛 楽器 袋 初心者 プロ 群馬県ふるさと伝統工芸品 [0088] 【ふるさと納税】篠笛楽遂 ドレミ調八笨調子 (C調) 姿仕上げ、笛袋と篠製こはぜ付き|甘楽町 篠笛 楽器 袋 初心者 プロ 群馬県ふるさと伝統工芸品 [0088]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/f103845-kanra/cabinet/0001-2000/26390088_1.jpg?_ex=128x128)