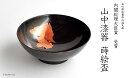騎旅《きりょ》は、はかどった。
丹波を去ったのは、先おととい。
ゆうべは近江《おうみ》愛知川《えちがわ》ノ宿《しゅく》だった。
そして今日も、春の日長にかけて行けば、
美濃との境、磨針峠《すりばりとうげ》の上ぐらいまでは、
脚をのばせぬこともないと、
馬上、舂《うすず》きかける陽に思う。
「おううい、おおいっ」
呼ぶ者があった。たれなのか、まだ遠い声である。
又太郎と右馬介とは、
「はて?」
手綱を休めて、きき耳すます。
たしかに、二度めの声も、
「高氏どの。高氏どの」
そう呼んだように思われる。
ところが、近づいたのを見れば、
まったく見も知らぬ人間だった。
緋総《ひぶさ》かざりの黒鹿毛に乗り、
薙刀《なぎなた》を掻《か》い持っている。
もちろん腹巻いでたち。
つまり旅行者当然な半武装をした四十がらみの武者なのだが。
——それはそれとして、相見るやいな、この男、
「わああああ。こりゃ卒爾《そつじ》を申した。
ごめん、ごめん。
……お呼びとめしたのは御辺じゃおざらぬ。
高氏ちがいじゃ、高氏ちがいじゃ」
と、独りでおかしがッている顔を斜めに振向けながら、
駒もゆるめず、連呼して、駈け抜けてしまった。
むッとしたに違いない。右馬介が色をなして。
「——うぬ、待てっ」とでも叫びそうに、
あぶみ立ちして、先を睨んだので、又太郎はあわてて制した。
「やれ待て。おかしいぞ、いまの武者は」
「言語道断。
いずれ近くの受領か郷《さと》武者ではござりましょうが、
礼をしらぬにも程がある」
「だが、高氏ちがいと申したのは解《げ》せぬ。
わしを又太郎高氏とは、どうして知るか」
「いかさま、それは」
「罠《わな》かもしれぬぞ。
俗に申すかまをかけてみる手はよくある。
めッたに、われから逸《はや》って手に乗るな」
道々には、ひとつの懸念がなくもなかった。
例の献上犬の事件である。
あの後始末は、伯父憲房がのみこんでくれてはいたが、
六波羅から鎌倉通牒となり、その結果、
さらに又太郎の無断上洛までが発覚となれば、
幕府は怒ッているにちがいない。
わるくすれば、又太郎の帰国を海道の途上で拉《らっ》し、
鎌倉表へ届けよ、などの令が、すでに出ていないとは限るまい。
が、今日の旅路を鬱々《うつうつ》と、
そんな先案じにとらわれている彼でもなかった。
春風に嬲《なぶ》らせてゆく面構えのどこかには
「……ままよ」といったふうな地蔵あばたの太々しさが、
いつも多少の笑みを伴っている。
そしてもっと大きな視野へその眉は向っていた。
この横着さは、彼がまだ元服前から、なんのかんのと、
折々に禅でいためつけられて来た那須の雲巌寺の客僧、
疎石禅師の鉗鎚《けんつい》のおかげといえぬこともない。
🌺🎼#春は紅、柳は緑 written by #香居
少納言のホームページ 源氏物語&古典 少納言の部屋🪷も ぜひご覧ください🌟https://syounagon.jimdosite.com
🪷聴く古典文学 少納言チャンネルは、聴く古典文学動画。チャンネル登録お願いします🪷